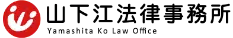昨今では労働者の就業意識が変化し,従来のように定年まで1つの会社で働き続けるという意識が薄れてきたと言われて久しい時代です。
それでもなお,就職して長年働いてきた会社から突然解雇を言い渡されてしまった場合,労働者は精神的にも経済的にも大きな打撃を受けることになると思います。
今回はそのような解雇に関する問題について労働者側の立場からお話したいと思います。
まず解雇とは,労働契約が継続中に使用者の一方的な意思表示によって労働契約を解約することです。
解雇の種類としては,大別すると「普通解雇」と「懲戒解雇」にわけることができます。
「普通解雇」は,使用者(会社)の一般的な解雇権に基づく解雇です。使用者の事業経営上の理由に基づくいわゆる整理解雇も一応はこの「普通解雇」の一種です。
「懲戒解雇」とは労働者が何らかの非違行為を犯した場合などに,使用者の懲戒処分としてなされるもので,就業規則の懲戒規定に基づいて行われます。
言うまでもなく,解雇は使用者の一方的な意思により労働者の生活に大きな打撃を与えるわけですから,以下で説明するとおり法律などにより解雇手続きや解雇事由に関して厳しく規制がされています。
まず,時期による規制として,使用者は労働者を解雇する場合,原則として30日前に予告するかあるいは予告の代わりに予告手当を支払わなければなりません(労基法20条1項)。
また,労働者が業務上負傷したり業務が原因で病気にかかったために療養している期間およびその後30日間について,原則として使用者はその労働者を解雇することはできません。
さらに女性が産前,産後に休業を申し出て休業している期間(労基法65条)およびその後の30日間についても同様に使用者は当該労働者を解雇することは原則できません。
さらに労働者の国籍・信条などを理由とする解雇(労基法3条),有給休暇を取得したことに対する解雇(労基法136条)も禁止されており,その他にも様々な解雇禁止規制が法律などで規定されています。
ただ,実際には使用者としても,上記の法規制にあからさまに反するような解雇を通知してくることはむしろ少なく,実際に問題となるようなケースとしては,上記のような規制には反していない場合です。
そのような場合に,労働者側の拠り所となるのが俗に解雇権濫用法理といわれる解雇の有効性を判断する審査基準です。
労働契約法16条には以下のような規定を置き,解雇を制限しています。
「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」
上記規定は以前から解雇の有効性について裁判で争われてきた際に裁判所が採用してきた見解を条文として明文化したものです。
解雇権濫用法理をかみ砕いて説明しますと,解雇には①合理的な理由と②社会的相当性が要求されているということです。
- についていえば,労働者の能力不足,成績不良,職務懈怠,職場規律違反などといったように会社の就業規則などで解雇事由として規定されている事実に当該労働者の日頃の勤務態度などが該当することだけでは解雇するには足りず,そういった労働者の事情が「雇用を終了させてもやむを得ないと認められる程度に達している」ことが求められているということです。
- については,実際にあった裁判例として,アナウンサーが2週間に2度寝過ごし放送できなかった放送事故を起こしたことを理由とする解雇について,解雇事由に該当することを認めながらも,本人のそれまでの勤務態度に問題が無く,他の労働者への処分と比較し均衡を欠くこと,本人が反省しているといった事情などから解雇するには社会的相当性がなく解雇を無効としたものがあります。
なお,経営不振の打開や合理化などといった使用者側の状況で行われるいわゆる整理解雇の場合には,労働者にもともと落ち度がないことから判例上さらに厳しく解雇が規制されています。
具体的には,整理解雇の場合には①人員削減の必要性②整理解雇を回避するために会社が努力したこと(例えば新規採用の停止・役員報酬のカット・希望退職者の募集などを経たこと)③解雇する労働者の選定基準および選定が公正であること④労働組合や労働者に対して必要な説明や協議を行ってきたことなどの要素に照らして解雇の有効性が判断されます。
いずれにせよ,解雇が労働者に与える打撃は大きいものですから,解雇は厳しく制限されているといえます。
突然会社から解雇されてしまった場合には,労働者としての地位を確認することや,解雇期間中の賃金を求めるなどの手だてが考えられます。
自分が勤めている会社から解雇を通知されることなど,当然誰しも経験したくはないことでありますが,もしもそのようなケースに遭遇してしまった場合,まずは当事務所までご相談ください。